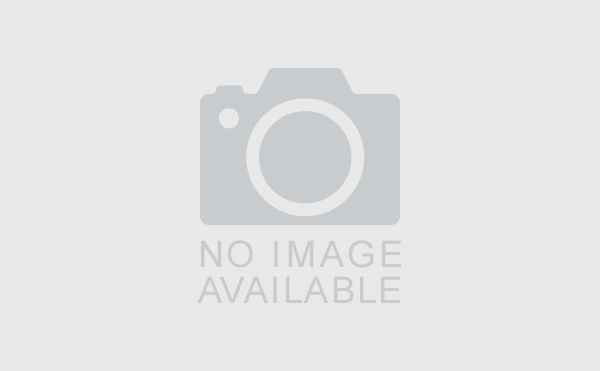破産会社と銀行の別段預金への振り替え合意と破産法上の相殺禁止について(東京高判R5.5.17)
本件(東京高判R5.5.17)は、破産法71条1項2号(破産手続開始前の支払不能後に契約を締結して破産財団に属する債務を負担した場合の相殺の禁止)に関連する判例です。
破産者甲社(以下「破産会社」)の破産管財人Xは、Y銀行に対し、破産会社の普通預金から振り替えられた別段預金および定期預金の合計約9000万円の払戻しと、これに対する遅延損害金の支払を求めて訴訟を提起しました。Xは、Y銀行が自己の貸金債権と破産会社の預金債権とを相殺したことについて、支払不能後に契約に基づき債務を負担したものとして、破産法71条1項2号に違反し無効であると主張した。なお、普通預金から別段預金への振り替えは、支払不能後であることが前提です。
一審(東京地判R4.11.9)がXの請求を棄却したためXが控訴しましたが、本判決も原判決を支持し、控訴を棄却しました。
本判決は、争点として、「別段預金」が新たな債務の負担に該当するか否かが正面から検討されまし。破産会社とY銀行の間では、住宅ローンの実行を受けた顧客からの請負代金が普通預金口座に振り込まれると、同日中にY銀行側で自動的に別段預金に振替えるという合意が存在していました。Xはこれを財産処分契約と捉え、Y銀行がその都度、破産会社に対して新たな預金債務(別段預金)を負担していたと主張した。
しかし、高裁は次のように述べてこの主張を退けました。
「本件普通預金口座には、平成30年10月26日から同年12月7日までの間に(管理人注:これは支払不能後です)、平時における取引と同様に、Y銀行から住宅ローンの実行を受けた顧客からの請負代金の支払としての振込入金があり、同振込入金が本件普通預金債務の負担原因となっているものであって、…このことをもって、上記顧客からの請負代金の支払としての本件普通預金口座への振込入金という債務の負担原因についてまで変更されたものと解することは困難である。」
すなわち、Y銀行が負担していたのは元々の普通預金債務であり、別段預金への振替は単にその取引条件の変更にすぎず、新たな債務の負担とはならないと判断しました。また、本判決はY銀行が破産会社からの預金払戻請求を受けた場合には「直ちに相殺の意思表示をしたというべきである」として、相殺適状も認めました。
破産法71条1項2号は、破産債権者による不当な債権回収を防ぐ趣旨であり、「支払不能後に破産財団に属する債務を新たに負担した場合」には相殺を認めないという制限が課されています。しかし、本件のように、元々存在する預金債務についての拘束性が高められたに過ぎない場合には、これに該当しないと判断したわけです。
本件は、預金の種別を変更することが、破産者にとって、新たな債務の負担と言えるかどうかが問題となった事案です。平時であれば、普通預金のまま置いておくことと、別段預金に振り替えることに、重要な差異はありません。このように平時であれば問題とならないことが、倒産となると大きな問題となってしまうことが時々あります。本件では平時における感覚が倒産時でも維持されるとしたわけですが、そうでないこともあるので、注意が必要である。
このへんが法律の面白いところでもあり、難しいところです。
さらに詳しく知りたい:破産債権者による相殺が禁止される場合と、その例外について(破産法71条の説明)は、こちらのサイトをご確認ください。